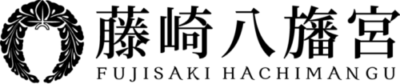- 手水の作法について
-
神社にお参りする際はまず、「手水舎てみずや」で手と口をすすぎます。昔から清らかな水は穢けがれを流すとされます。
はじめに左手を清めます。次に右手を清めます。
左手に水を受け、口をすすぎます。再び左手を清めます。
柄杓ひしゃくを縦に持ち、残った水で柄えを洗い流しま - お詣りの作法について
-
神社でも、家庭でも、神さまにお参りする際は、二拝(礼)二拍手一拝(礼)の作法で行います。神社や神棚の前で、姿勢を正してから腰を90度に曲げ、二回深くお辞儀をします。胸の前で両手を合わせ、右手指先を少し下げ、二回手を打ちます。もう一度深くお辞儀をします。※特殊な作法の社もございます。
- 玉串について
-
玉串とは、一年中青々とした葉が茂り、神さまが宿るとされる榊の枝に、紙垂しでや麻を結び付けたものをいいます。
榊の他に樫、松、杉、樅などの常緑樹を用いる地方もあります。
常緑の枝を用いるのは、神さまが木に宿るということから転じて、神さまに対するお供え物の意味もありますが、寧ろ清らかな誠心の気持ちを捧げる「しるし」と考えられます。
木偏に神と書いて「さかき」と読む榊には、「栄える木」、神社を神聖な場所として「境とする木」の意味もあります。 - 玉串礼拝の作法について
-
玉串を受け取り、玉串の先を時計回りに90度回して立てます。
左手を下げて根元を持ちます。このとき玉串に祈念を込めます。
玉串をさらに時計回りに回し、根元を神前に向けます。
玉串を案(机)の上に置きます。
二拝二拍手一拝の作法でお参りします