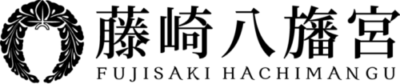藤 崎 八 旛 宮 例 大 祭

熊本に秋を告げる
千年の神祭
藤崎八旛宮例大祭
千年以上の歴史を持つ、神様が御自ら氏子地域にお越しになる大切なお祭りです。
いつの世も熊本の人々に敬われ、親しまれてきました。
「随兵」は加藤清正が随兵頭となり神幸行列を先導したことに由来すると伝わっています。
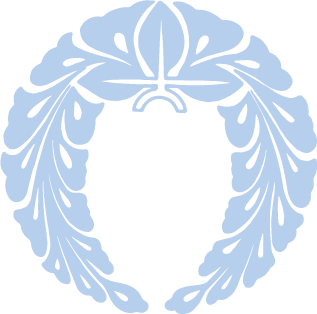
令和六年の例大祭につきまして下記の項目に情報を掲載いたします。

例大祭
開催情報
毎年の例大祭開催についての開催期間など開催情報のご案内を掲載しています。

神幸行列
御道筋
令和6年の例大祭の情報は現在ございません。
準備が整い次第掲載いたします。

飾馬の
奉納順位
令和6年の例大祭の情報は現在ございません。
準備が整い次第掲載いたします。

開催期間
交通規制
令和6年の例大祭の情報は現在ございません。
準備が整い次第掲載いたします。

関係資料
閲覧
令和6年例大祭 飾馬奉納に関する各種書類等はこちらからダウンロードください。

写真画廊
ギャラリ
神事から神幸行列の「随兵」「飾り馬」の奉納行列などのフォトギャラリー
|由来と歴史
千年以上の歴史をもつ藤崎八旛宮の例大祭(れいたいさい)は、昔から肥後(熊本)国の年中行事中最大の大祭として知られてきました。祭りは「放生会(ほうじょうえ)」を発祥として伝承されてきましたが、現在に至るまでに「随兵(ずいびょう)」などと呼ばれ、親しまれてきた歴史があります。
放生会と呼ばれるのは、明治時代の神仏分離令で仏教行事が一時的に廃止されるまでは、藤崎八旛宮でも例大祭が放生会として行われていたからで、今はその名のみをとどめています。

放生会古図(藤崎八旛宮所蔵)
|祭礼
「第一日祭」「第二日祭」「献幣祭」「神幸式」「奉賽祭」として例大祭では由緒ある古い伝統をもつ神事や祭祀が昼夜5日間に渡り行なわれます。そのほか献茶祭、和歌、俳句の献詠、生花の奉献、新町獅子、町鉾、子供神輿、神馬、飾馬の飾卸など多彩な行事も境内で繰広げられます。




|御神幸と随兵
祭りの中心となるのは、神輿にお迎えした神様が外へお出ましになる「御神幸(ごしんこう)」です。御神幸に「随兵(ずいびょう)」がお供をして護ることで行列となり、御旅所までの御道筋を歩んでいきます。
随兵は正確には、お供をする列の中に、大鎧を着て鍬形の兜を被り馬上で采配を振る「随兵頭」、その指示に従う百騎の「甲冑武者」、さらに長柄(ながえ)と言われる槍を持った陣笠・陣羽織姿の50人を指揮する裃(かみしも)に一文字笠を被った「長柄頭」「神幸奉行(みゆきぶぎょう)」などの威風堂々とした武者行列を指したものです。
朝の神幸を「朝随兵(あさずいびょう)」、夕の神幸を「夕随兵(ゆうずいびょう)と言いますが、それぞれ出陣の時の構え、帰陣の備えをかたどったものと伝えられています。
御神幸は卯の刻(午前6時)に御出発。約20000名の人と70頭余の馬で構成された行列は市街の目抜き通りへ繰り出し、お旅所へと向かいます。その姿は歴史絵巻にも例えられます。
9時頃に段山(だにやま)の御旅所に到着すると御祭儀が執り行われます。その後に能楽堂において主に喜多、金春二流の能楽が奉納上演され、午後2時半ごろ、御旅所を宮御立ちし、本宮へ還る御神幸が始まります。


朝夕共に御神幸は、沿道の人並みの中を四基の「御神輿(ごしんよ)」を中心に粛々と進みます。神職や総代、白の祭礼衣装に身を包んだ良民を表す「白丁(はくてい)」、百騎の随兵と長柄槍の武者が進み、その後に400年近く受け継がれてきた新町の獅子舞が独特の楽奏と伝統の舞を披露しながら進みます。最後尾が呼び物の「勢子(せこ 馬を追う人)」と飾り馬です。

団体ごとに趣を凝らした飾り馬と勢子の集団が、その生命力あふれる賑わいを奉納とするため、次から次に威勢よくまちを駆け抜け、ゴールとなる藤崎八旛宮へと向かいます。飾り馬となる馬たちはしっかりと安全が守られ、導かれていきます。
飾り馬はもともと供奉神職(ぐぶしんしょく 行列に参加する神官)が乗る馬に由来しますが、江戸時代には本宮と御旅所との距離が近かったため、乗馬せずに牽馬(ひきうま)として従える伝統となっており、空いた鞍の上の装飾が次第に大型になって現在のような紅白や青黄などのカラフルな色布の巻き飾りとなりました。
飾り馬に使われる馬は、細川藩の藩政時代には高禄の名家が駿馬に足軽や中間をつけて提供していました。決められた駈場で名家の名をかけてその俊足を競わせ、その見物で大層な賑わいを呈したそうです。明治以降は飾り馬は町方から奉納されるようになり、現在は氏子や参加団体が奉納しています。
藤崎八旛宮例大祭は千年以上前の生命をいつくしむ放生会の精神が、今もなお受け継がれ、熊本の皆様とこれからも共に在り続ける祭りです。